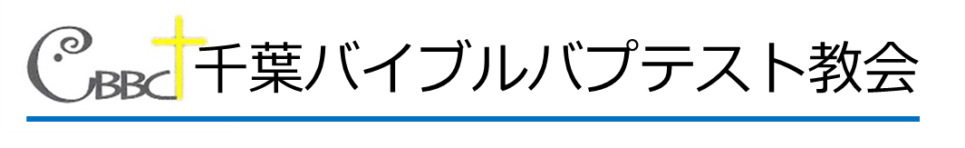本日より受難週に入ります。教会ではこの時期、福音書を読み、旧約聖書のイザヤ書の中に預言されている苦難のしもべの個所を拝読し、深い黙想の中に過ごします。磔刑はキリストの生涯の最も劇的な事件であるだけでなく、福音の本質を明らかに示す事件であるからです。共観福音書もヨハネ福音書も、皆一様に受難の様子を克明に記録しています。
共観福音者には、クレネ人シモンがイエスに代って十字架を担いで行ったとあります。一方、ヨハネ福音書には、イエスは一人で、最後までご自分の十字架を担いで、ゴルゴダの道を歩みぬかれたと記しています。ヨハネが描くイエスは、最も意志的で徹底的です。主イエスは「自分を捨て、自分の十字架を負い、そしてわたしについて来なさい。」(マタイ16・24)と命じられただけでなく、文字通りご自分も最後まで十字架を負われた、と強く語っています。
当時、受刑者は自分がかけられる十字架の横木を、自分で担いでいくのが一般的でした。イエスが十字架の横木だけを担がれたのか、それとも十字架を担がれたのかは意見が分かれるところです。古来キリスト教美術には、十字架を担ぐイエスが一般的です。主イエスは都の中を引き回されて「どくろ」とよばれる処刑場に来ました。その丘が人間の頭蓋骨を思わせる奇怪な形をしているところから、へブル語でゴルゴダ(頭蓋骨)と呼ばれました。十字架の上の罪状書には「ユダヤ人の王ナザレのイエス」とヘブライ語、ローマ帝国の公用語のラテン語、および当時の世界の通商語のギリシャ語の三カ国語で書かれていました。福音書は罪状書の事実を記すだけですが、ヨハネはこの三カ国語で記されたことに注目しています。それは、主イエスがユダヤ人の王であるだけでなく、ユダヤ人の世界を越え、当時のギリシャ、ローマの世界にも救いをもたらす救い主であることを、神の導きの中で書き留めたものと言えるからです。
2004年4月4日